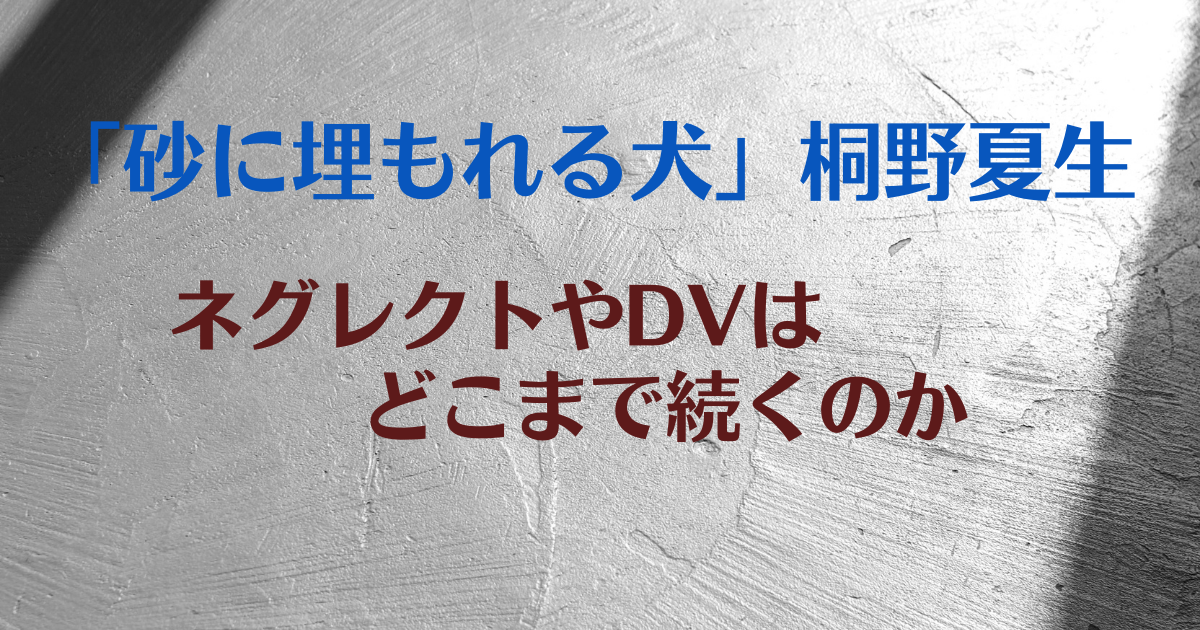
児童虐待、ネグレクト、なぜあの子は死ななきゃいけなかったのか…
という、事件のたびに繰り返される世間の声。
桐野夏生ならこう書くのか、という本です。
登場人物から物語を追っていこうと思います。
小森優真
主人公の少年で本来なら小学校六年生になっているはず。
でも、母親の亜紀が転居先の住民登録を怠っているせいで、小学校に行ってない。
しかも、家には食べ物がなく始終飢えている。
時々、この家の主の北斗と帰ってくるが、カップ麺と菓子パン数個を置いて三日間帰ってこないようなことが続く。
優真には、父親違いの弟 篤人がいる。
あまりの空腹で、置いていった食料を二人で一日で食べてしまう。
そこに帰ってきた亜紀に怒られる。
その騒ぎが気に入らない北斗に、青痣ができるほどの暴力を受ける。
亜紀は、追い出されるのを恐れて自身も暴力を加え、北斗を正当化する。
水道も電気も止まることがあるので、公園で水を飲んでしのいだり、体を拭くような生活だ。
もちろん、洗濯することも替えの衣服もないので汚れた身なりをしている。
そして、「家庭生活」というものを知らない。
亜紀
優真と篤人の母親なのだが、子育てをすることはない。
ねぐらを提供してくれそうな男について、どうにか生活をしている。
面倒なことを避け、楽な方に逃げて刹那を生きている。
優真と篤人の父親とも別れ、いや逃げ出されたのではないか。
成長と共に、その父親たちに似てくる二人の子供たちに恐れ、愛情の欠片も感じられない。
また、児童相談所や警察にネグレクトを通報されるのが怖く、バレそうになると逃げるという人物なのである。
しかし、亜紀もまたその母親のネグレクトを受けて育っている。
目加田夫婦
優真の家(北斗の家だが)の近くのコンビニを営んでいる。
夫婦には、二十歳になる重度脳性麻痺の娘、恵がいる。
妻洋子は娘の世話で付きっ切りなので、夫浩一は一人で店の経営をしている。
忙しいコンビニ店のあるマンションに引っ越して、少しでも睡眠時間を確保しようするほど疲れているのだ。
しかし、一人娘の恵に対しては、たとえ反応が薄かろうが愛情をもって見守り育てている。
優真と目加田の出会い
目加田のコンビニ店に学校があっている時間に、時々通ってくる優真と篤人。
ある日、消費期限が切れそうな弁当を廃棄しようとしていた目加田に「捨てるならください」と優真が申し出る。
規則では、廃棄処分する食品を売ることも譲ることも許されていない。
しかし、あまりに気の毒な身なりと幼さに弁当とおにぎりを渡してしまう。
それから、彼ら兄弟を気にして見ていたのだが、別の日に青痣のできた優真を見て警察に通報する。
優真は、児相から一時保護所に行くことになる。

熊沢花梨
熊沢家は、以前小学校四年生まで行っていた学校の近くにあり、優真から見るといわゆる温かい家庭だった。
姉妹の妹の方は、バレエを習っているのか大きな熊沢家のガレージから母親に送ってもらう姿を見ていた。
その子が、花梨でのちに転校先で出会うこととなる。
優真は、花梨に淡い気持ちを持ちながらもうまく会話もできず、その気持ちがやがてゆがんだものになっていく。
花梨は、中学で初めて優真を認識した。
はじめは、声をかけていたが、優真のぎこちなさや成育歴を知るにしたがって距離をとるようになる。
花梨だけでなく、その友達やクラスのみんなも優真に対し冷たい。
表立っていじめをするのではないが、優真は肌で感じここでも居場所のない気持ちを積み重ねる。
目加田夫婦が優真の里親になる
目加田の娘の恵が亡くなってしまった。
悲嘆にくれる妻洋子が、優真を里親として迎えたいと申し出る。
優真は、亜紀のことをとても憎んでいるので探し出してもらっても一緒に暮らす意思はない。
そして、目加田夫婦の里子になることとなった。
優真の過去とこれから
壮絶な虐待を受け続けてきた優真。
大人になるまでになんとか常識的な人間に育てたいと思う目加田。
大人を信じたり、大人に期待したりすることがなかった優真。
目加田家に行っても飢えずに住むところがあるなら、どうにか生活できるように振舞うのである。
飢えたり、寒い思いをすることはなくなったが、満たされない自分でもよくわからない思いを膨らませていく。
そして、不穏なことが起こりそうな予感。
ネグレクトやDVの連鎖
優真を育てられなかった母親亜紀は、鬼畜のような存在なのだけど、その亜紀もまた同じように育ってきたのです。
母親とか家庭とかモデルになるものを知らずに親になった亜紀。
優真も母親という女と、入れ代わり立ち代わり現れる、父親ではない男しか知らない。
「親も親なら子も子だ」というなら、だれが悪いというのだという優真の気持ち。
誰が悪いのか
優真が熊沢家を見るとき、アンデルセンの「マッチ売りの少女」が目に浮かびました。
暖かくおいしそうな食べ物とそれを囲む家族、穏やかな笑い声…
それを、凍てつく外から眺めているマッチ売りの少女。
小説では、桐野夏生氏が冷徹な筆致で描き上げていますが、現実はもっと厳しいものがあるのではないかと思いました。
「社会の最小単位は家庭です」
と、小学校五年生の時家庭科の時間に先生が言っていたことを今でも覚えています。
それぞれの家庭で、それぞれの「普通」があると思います。
児相や警察に行かなくて、ギリギリのところで生きている子供はいるのではないでしょうか。
目加田は、善良な市民です。
児童虐待事件で子供が亡くなったとき、「かわいそう」だと思うほとんど多数の私たちと同じ感覚の持ち主だと思います。
さらに、里親になろうとする行動もできる人です。
だから優真に「普通」を求めてしまう。
優真は、「普通」を知らないのです。
なぜなら、目加田が優真のような生活を送ったことのない大多数の人の一人だからです。
では、優真の魂は救われることがあるのでしょうか。
重いテーマの小説ですが、自分のフィールドだけで世の中は成り立ってないと考えさせられました。
表紙は、ゴヤの「砂に埋もれる犬」の一部です。
埋もれた犬の表情は、優真なのかだれなのか。